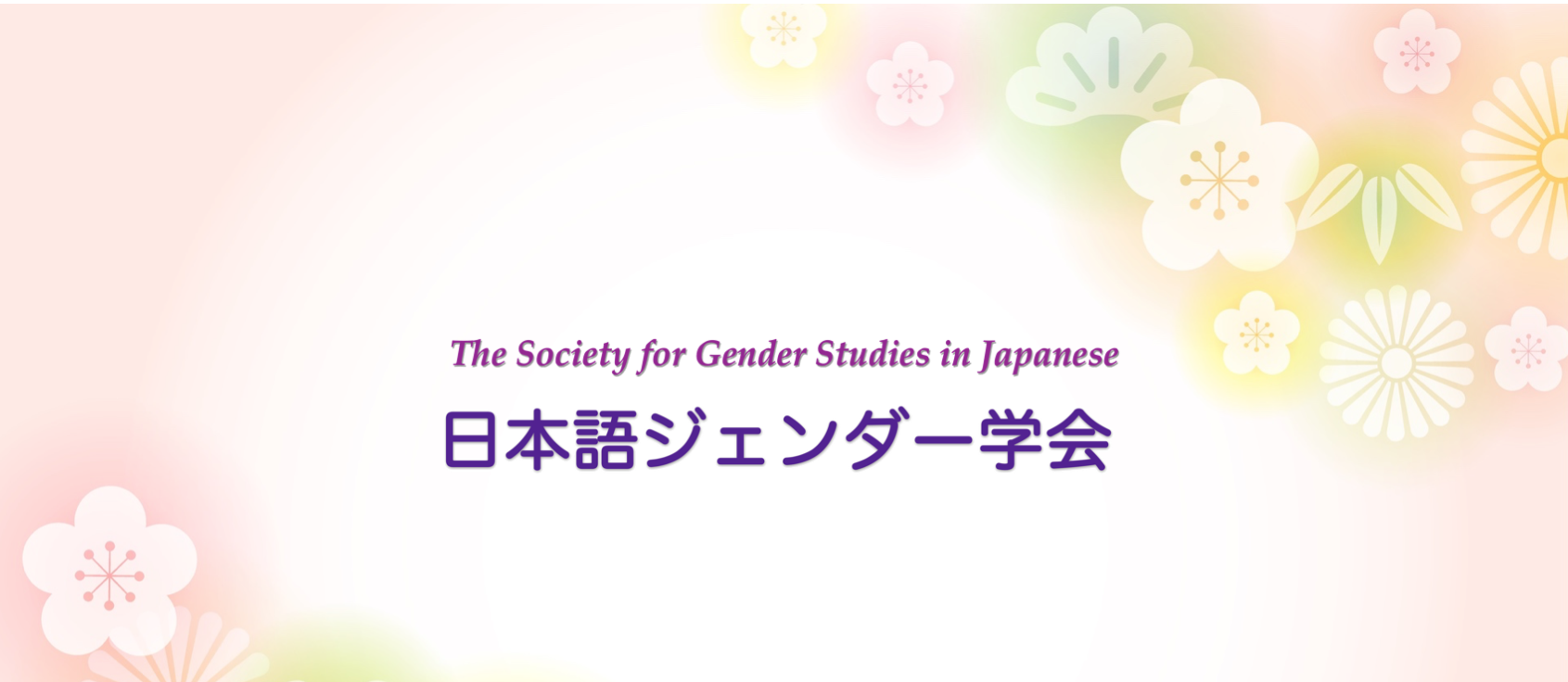【エッセイ】
俳句と女性
松井幸子
短歌は女性にむいているが、俳句は女性に適したジャンルではないといわれてきた。それは短歌は情におもむくままに流すことができるが、俳句は感情をせき止めるからだという。そのために、感情を抑制することが不得手な女性には不向きなジャンルであるというのがその理由であった。
俳句は明治になってから誕生したジャンルであるが、明治時代、ほとんど女性の俳人は存在していなかった。そのため、大正二年、高浜虚子は女性にも俳句をと「婦人十句集」という欄を「ホトトギス」に設け、周辺の女性に句作をすすめた。兼題(あらかじめ題を出すこと)の句を回覧によって選をするというもので、句会に参加するものではなかった。当時、良家の女性は伴もつれずに外出することは少なく、家族のための用件以外、ただ自分自身の趣味のために一人で出かけることはほどんど許されていなかったからである。
作品は日常の家庭生活に材を得たものが多く、「台所俳句」と揶揄された。だが、台所俳句という言葉は、最初は蔑称ではなく、自由に吟行に行けない女性に家庭を題材とすることを主眼とするという意であったが「所詮女の詠む下らない句」という意味となった。
大正半ばからは、長谷川かな女をはじめ杉田久女、竹下しづの女、中村汀女、星野立子、橋本多佳子といった優れた女性俳人が輩出してきたが、その多くは良家の妻であり、その数も男性に比べれば圧倒的に少数であった。
女性が急激に増加したのは、昭和四十年代からで現在では、女性の方が多い。その理由は幾つか想像できる。一つは、電化製品の普及に伴って、女性の社会的活動が容易になったといわれていることである。そして、杉田久女が家庭をおろそかにして俳句に熱中することは妻にあるまじき行為だという、いわれなき非難に悩まされたような、女性に対する偏見が次第に薄れてきたこともその一つであろう。
俳句だけで経済的に自立するのは困難である。大多数は趣味の範囲を越えないのが実情である。女性にとっての俳句の効用はまさにそこにあり、幾つかの「お稽古事」の一つとしての役割を果たすところに、多数の女性が俳句作に参加する基盤がある。
もちろん、俳句の文学としての存在価値を否定しているものではないことは言うまでもないが、それを支える読者としての句作者が多数の女性であるということなのであり、読者が作者を兼ねているところが、他の文学ジャンルと異なっているという特殊な要素があるためである。
底辺が拡がれば拡がるほど、そこから優れた女性俳人が多数誕生するのは当然の理で、それが現在の俳壇における女性俳人の隆盛の所以となっているということなのである。
日本の文学史を振り返ってみると、女性の活躍が目立つのは、平安から鎌倉初期の一時期だけである。この時代の女性が特に優秀であったわけではなく、貴族だけに限られてはいるが、才能を発揮する場があったからということは言うまでもない。
すぐれた才能を持ちながら、自らも周囲も気づくこともなく、あたら埋もれていった女性がいかに多かったかということを考えると、女性を取り巻く環境と周囲の意識がいかに大切かということを今さらながら感ずる昨今である。
2009年9月