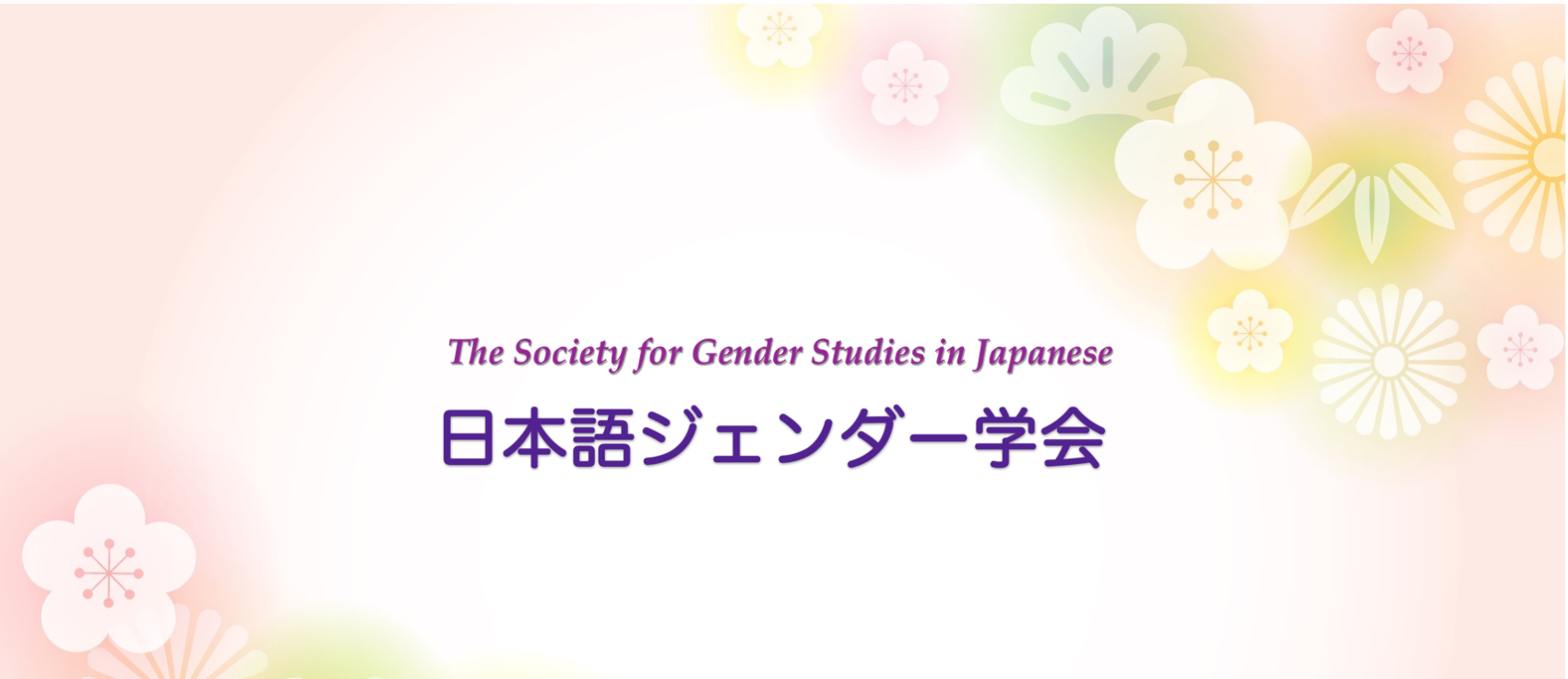★ 会員は学会誌最新号の丸ごとファイルを会員専用ページで閲覧 & ダウンロードできます。 最新号の各論文・講演概要などはこのウエブサイトにて2026年4月1日に一般公開されます。
![]() 第23号(2025)目次(日本語…英語)
第23号(2025)目次(日本語…英語)
PDFファイル 1MB
学会誌『日本語とジェンダー』第23号(2025年3月15日発行)
論文・講演の要旨(一部)
【研究ノート】
グルメ漫画の男女登場人物に割り当てられる「うまい」と「おいしい」― 社会的規範の遵守と逸脱― -------- p.1
稲永知世(佛教大学 准教授)
要旨
本稿では、「うまい」「おいしい」といった味覚評価表現とジェンダーの関 係性に注目し、グルメ漫画において、女性および男性登場人物に「うまい」「おいしい」が割り当てられる際の文脈を分析し、この選択が登場人物による社会的規範の遵守、あるいは逸脱と関係しているのかを考察した。分析の結果、女性登場人物の場合、「女性(らしい見た目の人)は女らしく振る舞うべきだ」という女らしさに関わる社会的規範が「おいしい」「うまい」の割り当てに大きく影響している一方、男性登場人物の場合、男らしさに関する社会的規範よりも親疎関係あるいは権力関係に関わる社会的規範が「うまい」「おいしい」の割り当てに影響していることを明らかにした。
【第24回年次大会 基調講演 要旨】
男女の話し方はどのように印づけられているか―ポピュラー・カルチャーを手がかりに― -------- p.15
金水 敏(大阪大学 名誉教授)
1.はじめに
言語における「有標性」とは、
(1) 中心的・標準的=無標
周縁的・非標準的=有標
のような対立として捉えられることがあるが、言語学における本来の意味としては
(2) 特別な標識がないもの=無標
特別な標識が付いたもの=有標
であったはずである。日本語の「女ことば」(女性語)は無標の「男ことば」に対して有標であると言われることがあるが(渋谷 2006, 中村 2007参照)それはもっぱら(1)の意味であり、(2)の意味には沿わない場合がある。例えば、人称詞の体系では、男ことばは「ぼく」「おれ」を持つが、女ことばは持たないという点で(2)の意味では女ことばが無標ということになる。
本講演では、日本語・標準語の「男ことば」「女ことば」の自称詞を中心に、ジェンダーがどのように印づけられているのかということを、主に歴史的経緯として追いかけ、そのことを通じて女ことばを「有標」と捉えることの是非を問うとともに、近代日本語がジェンダーをどのように印づけてきたかということを検証する。また、資料としては歴史的文献のほかに、ポピュラーカルチャー作品や大衆文化現象を多く用いる。....
【第24回年次大会 パネル・ディスカッション 要旨】
中国語の役割語とジェンダー -------- p.29
河崎みゆき(國學院大學大学院 非常勤講師)
1.はじめに
日本語は役割語が非常に豊富な言語である。中国語には役割語と呼べるものは存在するのだろうか。この問いに対して行った研究が拙書『漢語角色語言研究(中国語の役割語研究)』(2017年商務印書館、2024年ひつじ書房)である。パネル発表では本書に基づき、中国語の役割語について概観すると同時に、中国語の役割語とジェンダーの関係について問題提起を行った。
2.中国語の役割語研究
筆者は前掲書で、1.中国語の方言と人物像、2.中国伝統の「役割語」3.非言語行動(「体態語」)と人物像、4.非言語成語(体態成語)と人物像、5.命名と人物像、6.ネット上のキャラ現象とことば、7.「役割語」のリソースとしての中国の小学校語文(国語)教科書という観点から中国語の役割語の在り方にアプローチを試みた。
その結果、中国語にも日本語における大阪弁と商人キャラ、東北弁と田舎の人キャラのような方言と人物像の結びつきがあることや、中国伝統の「役割語」として「官僚ことば(官腔)」、「オネエことば(娘娘腔)」、「インテリことば・学生ことば(学生腔)」があることがわかった。....
役割語としての「僕」「あたし」―村上春樹の翻訳から― ------- p. 33
斎藤理香(ウェスタン・ミシガン大学 教授)
日本語の一人称代名詞は「僕」「あたし」「私」「おれ」「わし」など複数あるが、それらは、たとえば「僕」と常に自称する人物は比較的若くそれほど高い社会的立場にない男性、「あたし」はくだけた話し方をする若い女性、「わし」は高齢の男性、などと文学作品において登場人物の属性や性格を典型的に表すのに便利に使われることがある。これらは、フィクションにおける特定の人物像の発する言葉遣いが、その人物像にふさわしい話し方の特徴を示している(金水 2003:205)というのに該当し、その意味で「役割語」の一種といえる。本発表では、村上春樹の翻訳作品中の役割語「僕」と「あたし」に焦点を当て、それらが典型的な“役割語的役割” を果たしつつ、そのような役割とは異なる意味や効果を持つことについて考察した。
まず村上春樹の翻訳作品における「僕」についてだが、作品中の語り手である「僕」と、他の登場人物によって使われる「僕」とは切り分けた。言うまでもないことだが、英語ではほぼ “I” のみに限られる一人称代名詞を日本語へ翻訳する場合は、「僕」なのか「私」なのかは翻訳者に委ねられることになる。....
プリンセス物語と性別役割 ― 近世と現代のシンデレラ物語を中心に -------- p.36
谷口秀子(九州大学 名誉教授)
「ことばとジェンダー」研究は、社会の中の⾔語・言語使用・言語意識や態度における性差を問題化することで発展してきた。教育現場では、言葉と性差の実態や意識を単に反映するに留まらず、それらを強化・規範化する可能性も孕んでいることから、特に注意が肝要である。本発表では、アメリカにおける「ことばとジェンダー」をめぐる研究と教育について、具体的には「⼤学教育の現場で、性差と言語使⽤がどう認識されている(またはされていない)か」について、2、3の研究例の紹介と、自身(発表者)の研究・教育経験を基に考察した結果を報告する。
まず、アメリカの教育現場における「ことばとジェンダー」研究を概観する。Litosseliti( 2004)によると、1980〜1990年代の研究では、教室内の教師と⽣徒、あるいは⽣徒間のインターアクションにおける⼥・男の違いがいかに「差別」または「差異」を⽣じさせるかが特に問題化されている。....
【第23回年次大会 研究発表 要旨】
役割語を取り入れた日本語教育の意義とは― 日本語上級クラスでの実践を通して― -------- p.39
朴 智淑(トロント大学Assistant Professor)
増田恭子(ジョージア工科大学Professor)
山本裕子(愛知淑徳大学 教授)・
昨今の言語教育では、標準化を助長することに関する問題が議論されている(Doerr 2009:29)が、一方で言語の標準化や階層化を促すのではなく、流動的で多様なものとして捉えるためには、どのような活動や課題が有効か等については十分に報告されていない。
「役割語」をテーマにした理由としては、登場人物の一助になる役割語が時には偏見や差別意識の助長につながりかねない(金水2003:203)こと等が挙げられる。また、役割語は学習者の興味関心をひくものの、体系的な教育がなされているわけではない。さらに、現実社会で使われていることばとのズレがあることも多く、アニメ・マンガを通して学んだことばをそのまま使用し、問題が生じることもある(宿利2018:233)。
本発表では、カナダ・アメリカの大学の上級日本語クラス活動とその後行ったプロジェクト活動の実践と内容について報告する。....
幼児保育者及び保護者の語彙ジェンダー規範の傾向と揺れ―品詞別語彙アンケートとインタビュー調査をもとに― -------- p.42
渡辺倫弥(元淑徳大学留学生別科専任講師)
柴田 冴(元東京国際大学専任講師)
1.研究の背景と目的
近年、多様性や受容性への認識不足を要因とする日本の社会課題が顕在化し、ジェンダーギャップ指数は是正されない。固定的なジェンダー思想は言語を通じ教育にも根強く反映され、藤田(2004:343)は幼児は大人やメディアなどとの交渉の中で自らもジェンダー構築しているとし、幼児期のジェンダー教育の重要性を述べている。幼児に関連する日本語ジェンダー研究には、絵本のジェンダーバイアスはことばにも存在し、こどもが絵本からジェンダー規範を学んでいることを指摘した佐竹(2019:66)、保育環境と保育者のジェンダー観にどのようなジェンダーバイアスが存在するかを明らかにした金子・青野(2008:371)等があるが、幼児保育者、保護者双方を対象とし、品詞別で語彙のジェンダー規範意識に着目した研究は管見の限り見当たらない。
そこで、本研究は言語による社会化の開始時期にある幼児の日常的なやり取りを担う幼児保育者及び保護者が、特定の語彙に対してどのようなジェンダー規範意識を持っているか明らかにすることを課題とした。
児童作文に描かれる母親と父親についての一考察 -------- p.46
加藤恵梨(愛知教育大学准教授)
国際連合による「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標5に「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」ことが設定され、ジェンダーにおける平等を実現すべく、学校教育においてもジェンダー平等に関する内容が組み込まれるようになった。具体的には、「子どもたちは、教科書の中に描かれたジェンダーを疑いもなく吸収していく」(牛山2014:91)ことから、教科書がジェンダー構造の再生産機能を果たしていることが問題視され、ジェンダーに関する「隠れたカリキュラム」の見直しが行われている。例えば、2015年検定の中学校国語科教科書における性別役割の描かれ方についての研究では、従来指摘されてきた性別役割分業の「男(父)=仕事・外」「女(母)=家事・内」という構図から変化し、「家事も、仕事も」する母親像や、「力強さ」や「頼りがい」といった従来の男性ジェンダーイメージではなく、「悩める父親像」を描いていることが明らかにされている(中村2020:85-84)。さらに、『東京新聞』(2024年3月22日)によると、2025年度から中学校で使用される教科書には、LGBTQ など性の多様性についての記述が増え、登場する科目も広がった。....
「サザエさん」の女性登場人物が用いるジェンダー表現の考察 -------- p.50
増田恭子(ジョージア工科大学教授)
相場大毅(ジョージア工科大学学部生)
1.はじめに
日本語には文末詞や人称代名詞などジェンダー表現が多い。私たちは、会話の相手・状況・目的に応じて表現を選んでいるが、近年若者の言葉遣いが「中性化」していると言われている。二項対立方式を取り入れて実際の会話とドラマのセリフを比較分析した水本他( 2006:126-127)は、20代前半の女性が女性文末詞を使用するのは非常に稀だが、ドラマでは、ステレオタイプの女性(キャリア系・専業主婦)がわ系の女性文末詞をよく使用していると指摘している。また、60〜90年代のマンガを分析した因(2003:23)は、ジェンダー表現は人物造形に大きく影響していると述べている。
筆者らは、漫画のジェンダー表現の変化に興味があり、ロングセラーの漫画「サザエさん」のジェンダー表現の変遷を調査している。今回の発表の目的は、1946〜1952年(昭和21〜27年)と1973〜1974年(昭和48〜49年)の「サザエさん」の女性登場人物のサザエ・ワカメ・フネのセリフの文末詞と呼称詞の使用を分析し、年齢や場面によるジェンダー表現の実態を明らかにすることにある。
Copyright © 2025 The Society for Gender Studies in Japanese
All rights reserved